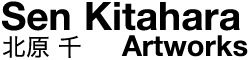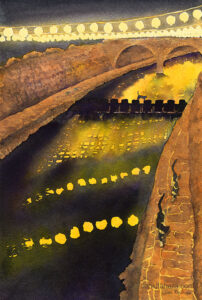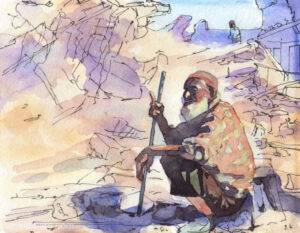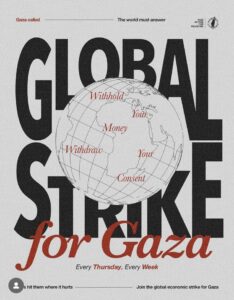油絵の具のメリット・デメリットは、油彩の最大の特徴である『油』に関わることがほとんどです。
油絵の具って?
油絵の具は、色の粉『顔料』を『油』で練った絵の具です。
チューブに入っている状態の絵の具は、全て油と混ぜられています。
アクリル絵の具や水彩絵の具と違い、水を含みません。
そのため、油彩で絵を描くときには水を一切使わず、代わりに油を使います。
絵の具を薄めたいときは、水の代わりに油を足して薄めます。
この油の成分が固まることによって、色の粉をキャンバスに定着させるのです。
油絵の具のメリット
油絵の具は水彩やアクリルに比べて特徴的な画材です。
メリットは以下の通りです。
- 存在感・現実感のある絵が描ける
- 綺麗なグラデーションが簡単に作れる
- 隠蔽力が高い
- 修正が簡単
- 作品が丈夫で長持ちする
それでは、詳しく説明していきます。
存在感・現実感のある絵が描ける
油絵の具で絵を描くと、作品に迫力が生まれます。
また、同じように描いていても、自然とタッチに奥行きを感じられる絵になっていきます。
黄色・オレンジ・赤色・茶色などの暖色系は、特に深い色合いになります。
画面に絵の具を置いているだけで、絵に説得力が出てくるのです。
これを他の画材で再現するのは、難しいでしょう。
綺麗なグラデーションが簡単に作れる
油絵の具の乾燥は、水彩等のように水分が蒸発して乾く類のものではなく、油が空気と反応し
て固化していくことを言います。
ですから、油絵の具は乾燥するまでに時間があります。
たっぷりあります。
そのため、グラデーションをじっくり作ることが可能です。
例えば、キャンバスの上半分に青色を塗って、それから下半分に白色を塗り、二色の境目を刷
毛で撫でてやるだけで、青から白の綺麗なグラデーションが作れます。
滑らかな絵を描こうと思ったとき、グラデーションが容易に作れる、ということは絶大な力
を発揮します。
背景から人物の肌、金属、流れる水の表現など、多岐にわたって使用することができるのです。
隠蔽力が高い
隠蔽力の高さも油彩の特徴です。絵の具の隠蔽力というのは、下の色を覆い隠す力のことです。
白いキャンバスに赤色を塗って、乾かしてから、その上から黄色を塗ったとき、黄色によって赤色がどれだけ隠せているか。
赤色が透けて見えて、黄色がオレンジがかったりしていたら、その黄色の隠蔽力は低いという
ことになります。
逆に、黄色の下に赤色の存在が全く感じられなかったら、その黄色は隠蔽力が強いことになるのです。
もちろん色によりますが、油絵の具は全般的に隠蔽力が高いです。
不透明色だったらもちろんのこと、透明色でも厚く塗ってやれば結構下の色がわからなくなります。
修正が簡単
隠蔽力の高さは、絵の修正の容易さに関わってきます。
油彩は、水彩やアクリルよりも修正が簡単な画材です。
きっちり乾かしてしまえば、上から全く別の絵を描くことができますし、乾く前であれば、一度置いた色を拭って描き直すこともできます。
作品が丈夫で長持ちする
油彩は、油が固化することによってカチカチになります。
乾燥したら、手で触っても画面が傷つくことがありません。
結構丈夫になるのです。
さらに、美術館にかなり古い作品が展示されていることからもわかるように、きちんと管理すれば長い間楽しむことができます。
油絵の具のデメリット
油彩はその特徴から、デメリットもあります。
主には以下の通りです。
- 乾くのが遅い
- 作業中は臭いが強い
- 油や絵の具の使い方に気をつける必要がある
- 長期的には黄変することがある
- 片付けが面倒
詳細をみていきましょう。
乾くのが遅い
まず、乾燥時間の長さです。
油彩は乾燥するのが非常にゆっくりです。
通常であれば、その日のうちに乾くことはありません。
色によっては一週間くらい経たないと、絵の具が手につく状態です。
これは、油彩の乾燥が油の固化であることと関係があります。
油が空気と反応して固化するのです。
つまり、化学反応で固まっていくのです。
この反応は気温にも左右され、夏であれば二日や三日、早ければ翌日には、ある程度触れる状
態になります。
しかし、冬場は倍ぐらいの時間がかかると見ておいた方がいいでしょう。
作業中は臭いが強い
次に厄介なのは、油絵の具を使うときの臭いです。
油彩に使う油には二種類あります。
乾性油と揮発性油です。
臭いのは揮発性油の方です。
乾性油にも臭いはありますが、気になるほどではありません。
揮発性油には、主に石油由来のペトロールと松脂由来のテレピン(ターペンタイン)がありますが、どちらも強い臭いを発します。
ただ、臭いの方向性は違っていています。
ペトロールは石油系の臭い、そしてテレピンは…これは例え辛いですね。
テレピンの臭いです。
強いていうなら、鼻を刺すような臭いといいましょうか。
ブランドによって、臭いの傾向は結構変わりますし、ペトロールはかなり臭いが抑えられた製
品も出ています。
使うものを選べば、ある程度快適に描くことができると思います。
ですが、乾燥前の油彩画と同じ部屋で生活するのはお勧めできません。
描き終わったら、別室に閉じ込める方がいいでしょう。
もちろん、乾いてしまえばそのような臭いは無くなります。
油や絵の具の使い方に気をつける必要がある
乾くと強靭な画面になる油絵の具ですが、使う上で決まりごとがあります。
決まりごとを守らなくても描けますが、後々になって画面がひび割れたり、はがれ落ちたり、という危険が出てきます。
慣れると大したことありませんが、初めのうちは覚えることが多いです。
長期的には黄変することがある
油彩は油を使います。
画材屋さんで、油絵の具用のオイルを見てもらうとわかると思いますが、割と黄色っぽいです。
揮発性油は無色透明ですが、乾性油はほとんどの場合、黄色から種類によっては茶色の色がついています。
これは油の性質なので仕方がありません。
実際に色を溶いていく上では、気になりません。
ですが、長期的に見るとこの黄味が増していくのです。
使うオイルにもよりますが、一番画面を強くする理想的な油であるリンシードオイルをあまり加工されていない状態で使うと、長期的には作品の黄色みが強くなることが多いです。
なお、黄変が穏やかであると言われているポピーオイルも、全く黄変しないわけではありません。
オイルの色と油彩は切り離せない関係にあると言えます。
片付けが面倒
油絵の具は片付ける際も一手間かかります。
筆やパレットを洗面所でざっと洗って…というわけにはいきません。
それぞれ絵の具を拭き取ってから、筆については洗う用の油できれいに絵の具を落としてやります。
慣れれば大して気になりませんが、水彩などと比べると、やはり面倒です。
おわりに
以上が、油絵の具を使う上でのメリットとデメリットです。
油を使うという特性上、多くの人に馴染み深い水彩とは全く違った性質が見えるかと思います。
一見、手間がかかりそうで取っつきづらそうに見ます。
しかし使ってみると、これほど自由に描ける画材もないのではないか、と思わせるほど、描き手の要求に応えてくれる画材です。
慣れるととても楽しいので、ぜひ使ってみてほしい画材です。